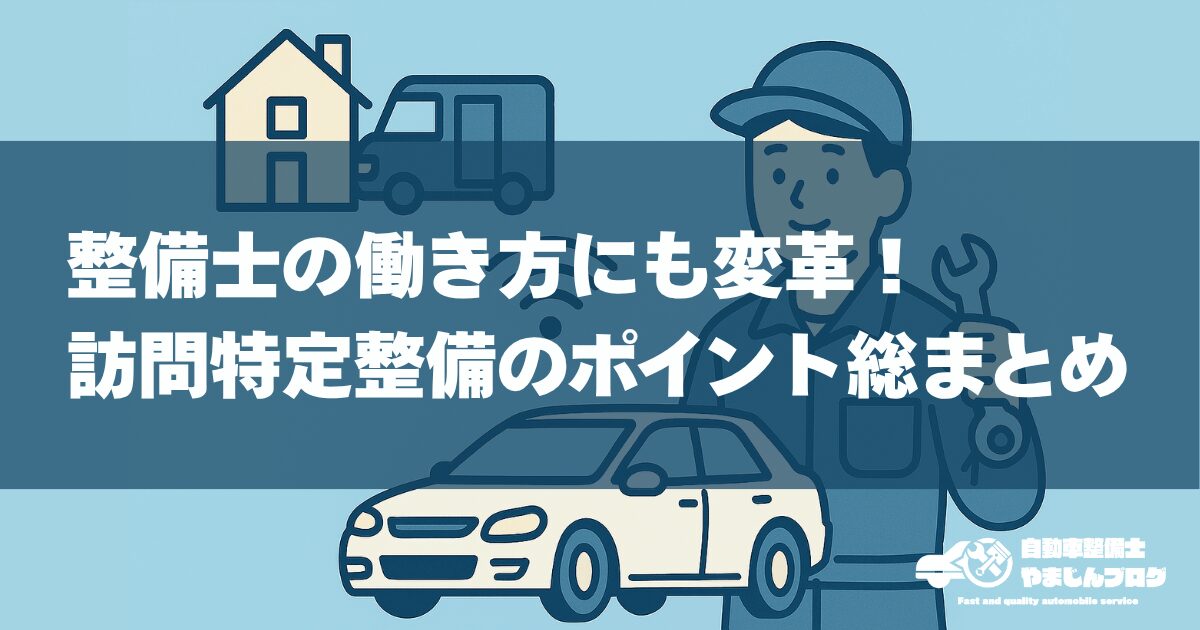2025年6月30日から施行された「訪問特定整備」制度について、「はじめて耳にする」「なんだか難しそう」と感じ、具体的な情報を探している人も多いのではないでしょうか?
私たち整備業界にとっては、まさに「何が変わる?」「どう対応すればいい?」と頭を悩ませる大きな変化ですよね。
私自身、整備歴26年、そして整備工場を10年間経営したことのある現役の自動車整備士として、この新しい制度が自動車整備事業にどのような影響を与えるのか、深く理解したいと考えています。
本記事では国土交通省が新設する「訪問特定整備」制度の概要から、訪問特定整備(フルパッケージ)と限定訪問特定整備の具体的な違い、さらには実施に際しての厳格なルールと要件までを、整備事業者の視点に立って、徹底的にわかりやすく解説します。
この記事を読めば、新しい制度への理解を深めることで、自身の事業に「訪問特定整備」をどのように取り入れ、顧客への新たなサービス提供や、ビジネス展開に繋げていけるのかを具体的に考えることができるでしょう。
訪問特定整備とは「認証工場が事業場外で特定整備を行う制度」

- 整備工場へ車を持ち込む手間の削減
- 人手不足の運送事業者などへの整備士派遣による生産性の向上
これまで、エンジンやブレーキなどの「特定整備」は、国の認証を受けた「認証工場」の事業場内でしか行うことができませんでした。
新設される「訪問特定整備」制度は特定整備のルールに例外を設け、認証工場に所属する自動車整備士がユーザーの自宅や運送会社の作業場など、事業場以外の場所を訪問して特定整備を実施することを可能にするものです。
訪問特定整備には作業を行う場所の設備状況に応じて以下の2種類があります。
訪問特定整備(フルパッケージ)
- 場所の要件
- 運送会社の整備作業場など、認証工場の設備要件(道路運送車両法施行規則第57条第1号から第5号に掲げる基準)を満たす場所で実施可能です。
- 作業範囲
- すべての特定整備を行うことができます。作業範囲には特定整備を伴う12ヶ月点検などの法定点検整備も含まれます。
車検そのものや、車検に付随する24ヶ月点検などの整備は対象外
限定訪問特定整備
- 場所の要件
- ユーザーの自宅駐車場など、認証工場の設備要件を満たさない場所でも可能です。ただし、「安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ることのできる場所」に限定されます。具体的には、平滑に舗装されていることや、周辺を通行する第三者が進入できないような措置が講じられていることなどが求められます。
- 作業範囲
- ブレーキパッドの交換(事故、故障等により摩耗または損傷したものに限る)、発電機(オルタネーター)の交換、大型特殊自動車のステアリングホースの交換
限定訪問特定整備も車検そのものや、車検に付随する24ヶ月点検などの整備は対象外で、特定整備を伴う法定点検整備もできません。
エンジンマウント等の取り外しは、オルタネーターまたはスターターモーター交換に必要な限度でのみ認められます。
訪問特定整実施ルールと要件

訪問特定整備を行う上で、守るべきルールが厳しく定められています。
実施主体は認証工場のみ
個人の整備士や認証を受けていない事業者は訪問特定整備を行うことはできません。
責任の所在
万が一、事故やトラブルが発生した場合の責任は派遣元の認証工場が負います。

現場の整備士個人が責任を負うことはありません。
整備士の要件
各事業場ごとに整備主任者のうち少なくとも一人を「訪問特定整備等管理者」として任命する必要があります。
- 訪問特定整備士
- 1級または2級の自動車整備士資格と3年以上の特定整備の実務経験が必要
- 準訪問特定整備士
- 3年以上の実務経験など一定要件を満たす3級整備士は、同行する訪問特定整備士の指示の下で作業が可能
訪問特定整備士は「訪問特定整備等教育」を2年ごとに受講し、運輸支局長などに届け出ることが義務付けられています。
届出と情報公開
作業開始の前日までに運輸支局長などに必要事項を電子メールで届け出る必要があります。変更があった場合も同様です。
届け出たことを示す証票を自社のウェブサイトや訪問整備の作業場所で表示することが義務付けられます。
ウェブサイト上で訪問特定整備に関する作業工賃、部品価格、旅費などの料金説明を掲載が必要です。
記録と保存
訪問特定整備料金の概算見積もり、訪問場所、作業前後の車両、交換部品の画像データ、請求書などの写しを2年間保存することが義務付けられ、記録は原則として電磁的記録(デジタル)で行うことが求められます。
作業場所の確認
作業開始前に事業者の責任のもと作業場所が安全性の確保、整備品質の担保、環境保全の要件を満たしているかを入念に確認することが義務付けられています。
訪問可能な範囲
原則として同一の都道府県内または自動車によりおおむね1時間以内とされています。
違反時の行政処分
要件に違反した整備事業者には行政処分が科されます。
業界からの懸念と国土交通省の見解
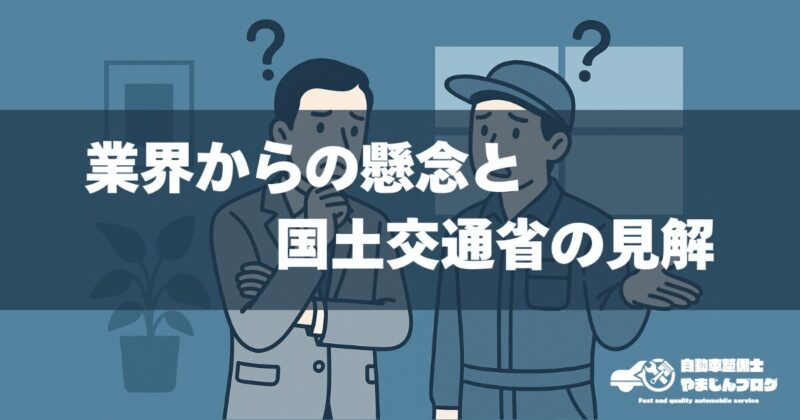
整備業界からは訪問特定整備制度に対して様々な懸念の声もあがっており、国土交通省はそれらの意見を踏まえ、以下のような対応方針を示しています。
- 安全性・品質の確保:
- 懸念: ジャッキアップ時の床強度、不整地での作業、悪天候、整備士の健康問題、整備不良車増加のリスクなど。
- 国交省の見解: 作業場所は「平滑に舗装されていることや周辺を通行する第三者が進入できない措置」など具体的な要件を別途明示し、事業者の責任で入念に確認することを義務付けます。
- 環境保全:
- 懸念: 油や廃液、粉塵の流出による環境汚染。
- 国交省の見解: 限定訪問特定整備の作業内容は基本的に油等が流出しないものに限定し、作業場所は公害防止が図れる場所に限定します。
- 責任の所在の曖昧さ:
- 懸念: 事故発生時の責任の明確化。
- 国交省の見解: 事業者が責任を負うことを明確にしています。
- 「野良整備」の横行:
- 懸念: 未認証事業者や資格を持たない個人による不適切な整備が増えること。
- 国交省の見解: 訪問特定整備は認証工場に限定されており、未認証事業者の撲滅も意図しています。作業の都度、写真撮影・画像データ保存を義務付け、事後的な規制を強化します。
- 既存認証工場への影響:
- 懸念: 多額の設備投資をしてきた既存工場の意義が薄れる、低価格競争の激化、整備品質の低下、整備士の賃金低下。
- 国交省の見解: 訪問特定整備は作業場所や内容が限定されているため、多くのユーザーは従来通り認証工場への入庫が必要です。また、工賃が不当に下がらないような措置も別途講じます。
- 整備士の労働環境悪化:
- 懸念: 屋外での悪条件下での作業、無理な依頼によるプレッシャー、残業増加、整備士への負担増と離職加速。
- 国交省の見解: 事業者は整備士の労働状況を考慮して適切に判断し、過度な負担を与えないようにします。
まとめ|認証工場に期待される今後の展望

訪問特定整備制度はユーザーの利便性向上や整備業界全体の生産性向上といったメリットをもたらす可能性があります。
エンジンがかからない車の出張修理や、自社整備工場を維持できない運送事業者などへの対応は、新たな需要を生むかもしれません。
しかし、その成功は私たち認証工場が厳格なルールを遵守し、安全確保、整備品質の担保、そして環境保全を徹底することにかかっています。
制度開始後も国土交通省は市場状況を注視していくとのことなので、整備業界からも現場の声を上げ続け、より良い制度運用に貢献していくことが重要です。
訪問特定整備制度を正しく理解し、自社の強みや顧客ニーズに合わせて活用していくことで自動車整備業界の発展につながることを期待しています。